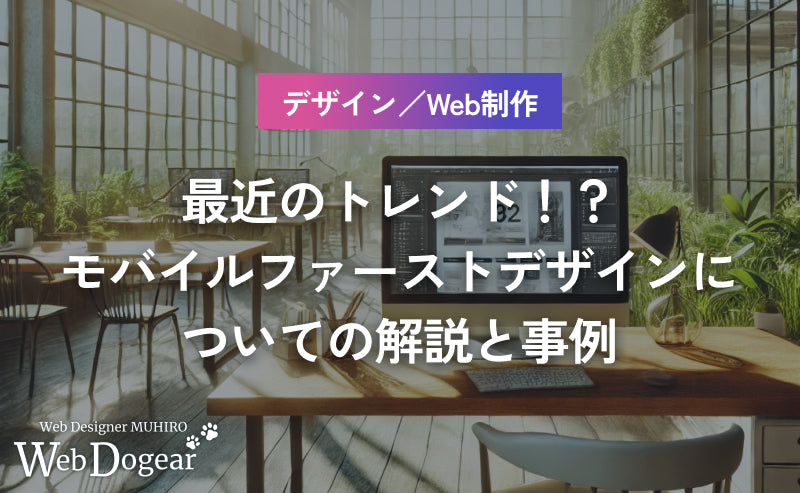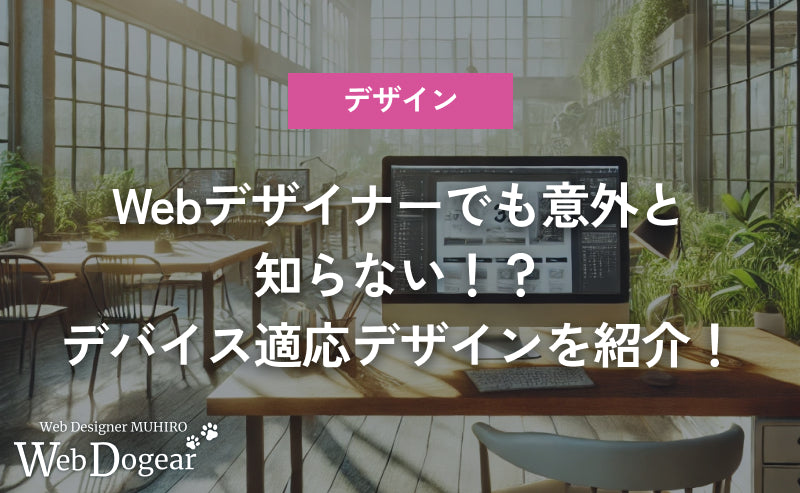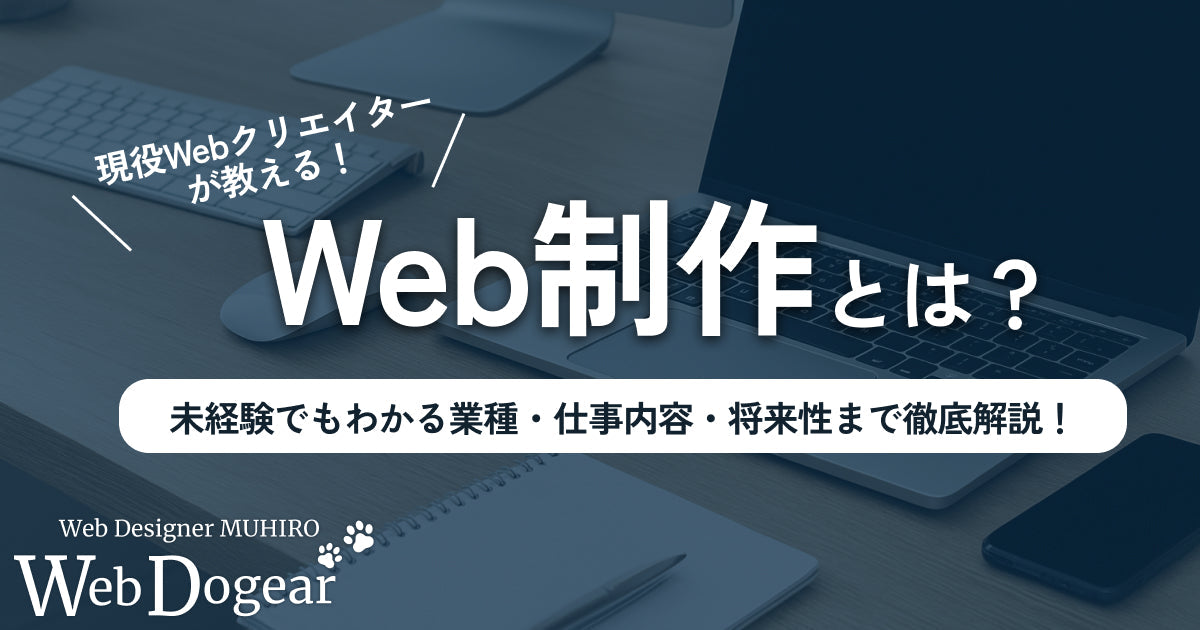【2025年最新】初心者向け|Webサイト制作の流れをゼロから徹底解説!
Published: Updated:
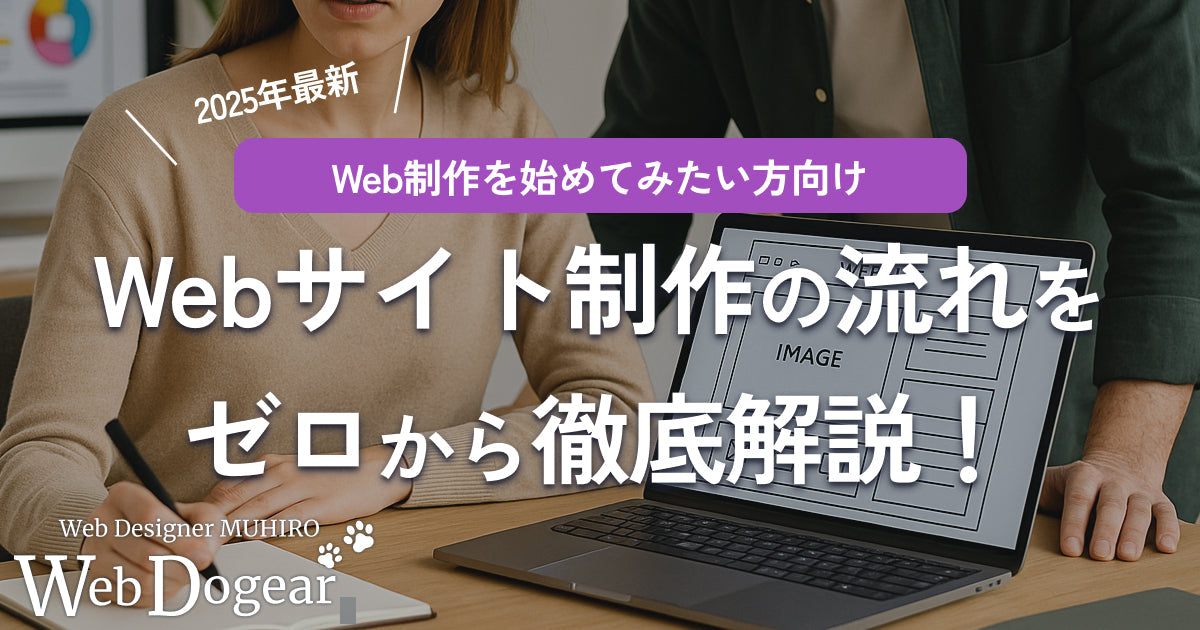
こんにちは、Webデザイナーの 夢拓(Muhiro)です。
初めてWebサイト制作に関わるとき、多くの方が「何から始めればいいのか」「どの工程で何をすればいいのか」と悩まれます。
特に初心者や発注担当者の場合、制作の流れを理解していないとスケジュールの遅延や品質の低下につながることもあります。
この記事では、最新のWeb制作フローを初心者にもわかりやすく解説し、実務で役立つ具体的なポイントを整理します。
この記事では、企画から公開、運用までの各ステップを事例や注意点とともにご紹介します。
Web制作の全体像を知ることで、制作会社とのやりとりがスムーズになり、プロジェクトの成功率が格段に高まります。
Webサイト制作は、ただデザインを作って公開するだけではありません。
企画段階から情報設計、デザイン、実装、テスト、公開、運用まで複数の工程を経て完成します。
各工程を理解することで、発注側も制作側も無駄な修正や誤解を減らすことができます。
このガイドを読めば、あなたの制作プロジェクトはよりスムーズに、そして効果的に進められるでしょう。
この記事を読んで、Webサイト制作の実践的なテクニックを使用して最適かつ高度で柔軟なWebサイトを制作いただけるようになります!
Index
[ CloseOpen ]
Webサイト制作の全体像と目的の整理
Webサイト制作の第一歩は、全体像を把握し、明確な目的を設定することです。
目的が不明確なまま進めてしまうと、デザインや機能の方向性がぶれ、最終的に成果が出ないサイトになるリスクがあります。
例えば、企業のコーポレートサイトはブランドイメージの確立や信頼感の向上が目的となりますが、ECサイトでは売上向上や購入体験の最適化が重要になります。
さらに、採用サイトは応募者に企業の魅力を伝えることが主なゴールです。
このように、サイトの種類ごとに目的や評価指標(KPI)は異なります。
目的が明確になれば、後の工程でデザインやコンテンツの方向性がブレずに進行できます。
企画・要件定義|サイトの方向性を固める
企画段階では、ターゲットユーザーを設定し、そのニーズに応えるためのコンテンツや機能を洗い出します。
要件定義では、サイト構造や必要なページ数、各ページの目的を明確化します。
ここでは、プロジェクトのスケジュールや予算の見積もりも行い、関係者間で合意を形成します。
要件定義のドキュメント化は非常に重要で、後工程での認識齟齬を防ぐ効果があります。
また、競合サイトの分析を行うことで、自社サイトの差別化ポイントを明確にできます。
最新のトレンドとしては、アクセシビリティやSEOを初期段階から考慮した要件定義が一般的です。
予算とスケジュール管理|プロジェクトを成功に導く計画立案
Webサイト制作を成功させるためには、適切な予算とスケジュール管理が不可欠です。
工数見積もりと予算計画
各工程の工数を正確に見積もり、追加費用が発生する可能性があるケース(仕様変更、コンテンツの大幅増加、複雑な機能追加など)を事前に想定しておくことが重要です。
リスク管理とコンティンジェンシープラン
また、技術的な問題や外部要因による遅延に備えたリスク管理とコンティンジェンシープランの策定により、プロジェクトを予定通りに完了させることができます。制作会社との契約時には、これらの点を明確に取り決めておくことをお勧めします。
ワイヤーフレーム作成|情報設計の基本
ワイヤーフレームは、サイトのレイアウトや情報の配置を示す設計図です。
デザイン前の段階で作成し、情報の優先順位やユーザー導線を確認します。
これにより、ユーザーが必要な情報にスムーズにアクセスできる構造を作ることができます。
UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)の観点から、リンクの配置やボタンサイズ、テキスト量なども検討します。
最新では、FigmaやAdobe XDなどのクラウドツールを使ってリアルタイムで共有・修正できる制作環境が増えています。
こうしたツールを利用すれば、クライアントやチームメンバーと迅速に意見交換が可能です。
デザイン制作|ブランドと世界観を形にする
デザイン制作では、ブランドカラーやロゴ、フォントなどを基に、企業やサービスの世界観を視覚的に表現します。
この段階では、PC・スマホ・タブレットなど様々なデバイスでの見え方を考慮するレスポンシブデザインが必須です。
新のトレンドとしては、ミニマルデザイン、ダークモード対応、グラスモーフィズムなどがあります。ニューモーフィズムは2020年頃に注目されたスタイルですが、視認性やアクセシビリティの課題があり、現在は控えめな使い方にとどめ、フラットやマテリアルデザインの方が広く支持されています。
ただし、ニューモーフィズムは実用性の観点から近年は慎重に採用されており、アクセシビリティを優先したフラットデザインやマテリアルデザインが主流となっています。
また、アクセシビリティを考慮し、色弱者でも情報が正しく伝わる配色や文字サイズの設定も重要です。
デザイン案は静的画像だけでなく、プロトタイプとして動きを確認できる形で提案することが増えています。
これにより、実装前にユーザー体験をテストできるため、完成度の高いデザインが可能になります。
WCAG準拠のアクセシビリティ実装
具体的には、WAI-ARIA属性の適切な実装、キーボードのみでのナビゲーション確保、スクリーンリーダーへの対応など、WCAG 2.1ガイドラインに準拠した実装を行うことで、すべてのユーザーにとって利用しやすいサイトを構築できます。
コーディング|デザインをWeb上に実装する
コーディングでは、HTML・CSS・JavaScriptを使ってデザインをブラウザ上で再現します。
HTMLはページの骨組みを作り、CSSでスタイルを設定、JavaScriptで動的な動きを加えます。
また、CMS(WordPressなど)を導入する場合は、テーマ構築やプラグイン設定もこの段階で行います。
モバイルファーストの設計や、Core Web Vitals(LCP、CLS、FID/INP)を意識した軽量なコードが近年の重要ポイントです。
これらの指標はGoogleの検索ランキングにも影響するため、ページ読み込み速度やレイアウトの安定性を考慮したコーディングが必須です。
コーディング規約をチームで統一することで、保守性が高く、エラーの少ないサイト運営が可能になります。
また、Gitなどのバージョン管理システムを活用して、複数人での効率的な開発体制を整えることも推奨されます。
モダンな開発アーキテクチャ
近年では、ヘッドレスCMS(Headless CMS)を活用したJAMstack(JavaScript, APIs, Markup)アーキテクチャや、コンポーネント駆動開発による効率的な制作手法も注目されています。これらの手法は、パフォーマンスとセキュリティの向上に寄与します。
パフォーマンス最適化の具体的手法
具体的には、画像の最適化(WebP、AVIF形式の活用)、CDN(Content Delivery Network)の導入、適切なキャッシュ戦略の設計、遅延読み込み(Lazy Loading)の実装など、総合的なパフォーマンス改善が求められます。
テスト・動作確認|公開前の品質チェック
サイトが完成したら、公開前に入念なテストを行います。
この工程では、リンク切れや表示崩れ、フォームの送信動作などを全ページで確認します。
また、PC・スマホ・タブレットといった複数のデバイスやブラウザ(Chrome、Safari、Edge、Firefoxなど)で表示や動作を検証するクロスブラウザテストも必須です。
機能テストとユーザビリティテスト
基本的なリンク切れや表示崩れの確認に加えて、実際のユーザーの行動を想定したユーザビリティテストも実施しましょう。
フォーム送信後のサンクスページ表示や、エラーメッセージの挙動確認も忘れてはいけません。
パフォーマンステストとSEOチェック
最新の品質管理では、自動テストツール(Lighthouse、PageSpeed Insightsなど)を使って速度やアクセシビリティもチェックします。
この段階での不具合修正は、公開後のトラブルを防ぎ、ユーザー体験を損なわないための重要なプロセスです。
公開|本番サーバーへのアップロード
テストが完了したら、いよいよ本番サーバーへアップロードしてサイトを公開します。
このとき、ドメイン設定やSSL証明書の導入(https対応)を必ず行い、セキュリティと信頼性を確保します。
公開後は、Google Search Consoleへのサイト登録と、XMLサイトマップの送信を行い、検索エンジンにインデックスされるようにします。
また、SNSやメールマガジンなどを活用して公開告知を行い、初期アクセスを確保することも効果的です。
公開後すぐにアクセス解析ツール(Google Analyticsなど)を設置して、訪問者データを取得できる状態にしておくことも忘れないようにしましょう。
法的コンプライアンスの確保
同時に、プライバシーポリシーの設置、Cookie使用に関する同意バナーの実装(GDPR、個人情報保護法対応)、利用規約の策定など、法的コンプライアンスも確実に対応する必要があります。
運用・改善|作って終わりにしないサイト管理
Webサイトは公開して終わりではありません。
定期的にコンテンツを更新し、ユーザーのニーズや検索エンジンの評価に応える必要があります。
アクセス解析データを元に、人気のあるページや離脱率の高いページを分析し、改善施策を講じます。
例えば、ページの読み込み速度を改善したり、コンテンツをリライトしてSEO効果を高めたりすることが有効です。
また、セキュリティアップデートやプラグイン更新も継続的に行い、脆弱性を防ぐことが重要です。
セキュリティ対策の実装
具体的には、XSS(クロスサイトスクリプティング)、CSRF(クロスサイトリクエストフォージェリ)、SQLインジェクション等の攻撃に対する対策を実装し、WAF(Web Application Firewall)の導入も検討しましょう。定期的なサイトバックアップの取得と復旧テストも欠かせません。
継続的な改善施策
具体的には、定期的な脆弱性診断の実施、A/Bテストによる改善効果の測定、ユーザーフィードバックの収集と活用、検索エンジンアルゴリズムの変更への迅速な対応などが含まれます。
データ分析と戦略的改善
PDCAサイクルを回し続けることで、サイトの価値を長期的に高めることができます。アクセス解析データから得られる定量的な情報と、ユーザーインタビューなどから得られる定性的な情報を組み合わせることで、より効果的な改善策を立案できます。これらの継続的な取り組みにより、競合他社との差別化を図ることができます。
スポンサードリンク
独学だけでは挫折しそう…そんな方はWeb制作スクールの活用がおすすめです。
プロ講師の指導と学習環境で、効率的にスキルを身につけられます。
下記リンクから人気スクールをチェック!
この記事に関連するよくあるご質問
-
QWebサイト制作にはどれくらいの期間がかかりますか?
-
A小規模サイトなら1〜2ヶ月、中〜大規模サイトでは3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。
工期はページ数や機能の複雑さ、準備状況によって変動します。
-
Q企画や要件定義では何を決めますか?
-
Aサイトの目的、ターゲットユーザー、必要な機能、コンテンツの種類を決定します。
この段階で方向性を固めることで、後の工程がスムーズになります。
-
Qワイヤーフレームはなぜ必要ですか?
-
Aワイヤーフレームはページ構成や情報の優先順位を視覚化する設計図です。
デザイン前に作成することで、UI/UXの方向性を関係者間で共有できます。
-
Qデザイン制作では何を意識しますか?
-
Aブランドカラーやフォント、レイアウトを使い、ターゲットに合った世界観を表現します。
レスポンシブ対応やアクセシビリティも重要です。
-
Qコーディングではどんな作業をしますか?
-
AHTML・CSS・JavaScriptを使い、デザインをブラウザで再現します。
CMSの導入や動的機能の実装もこの段階で行います。
-
Qテスト工程では何をチェックしますか?
-
A表示崩れ、リンク切れ、フォーム動作、スマホやタブレットでの表示確認などを行います。
パフォーマンスやセキュリティの検証も重要です。
-
Q公開作業で必要な設定は何ですか?
-
Aドメイン設定、SSL化、Google Search Console登録、XMLサイトマップ送信が一般的です。
公開告知やSNS発信も効果的です。
-
Q公開後の運用で大切なことは何ですか?
-
A定期的なコンテンツ更新、アクセス解析、SEO改善、セキュリティ対策が重要です。
継続的な改善がサイトの価値を高めます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回の記事では、Webサイトが完成するまでの全工程を初心者向けに解説しました。
今回のポイントをまとめますと、次のとおりです。
他にもWeb制作に関する技術や実用テクニックを随時発信しています。
「役に立った」と思っていただけた方は、ぜひブックマークやSNSでのシェアをお願いいたします!
最後までお読みいただきありがとうございました!
免責事項
- 当ブログでは、執筆者の経験に基づいた技術情報や知識を提供していますが、その正確性や普遍性を保証するものではありません。情報は執筆時点のものであり、技術の進展により古くなる可能性があります。これらの情報を利用する際は、自己責任で行ってください。必要に応じて専門家の助言を求めることをお勧めします。
- 当ブログで提供するプログラムコードは、執筆者の最善の知識に基づいていますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。コードの利用や実行により生じた損害や問題については、一切の責任を負いかねます。コードの使用は、自己責任で行ってください。
- 当サイトで使用しているスクリーンショット画像について、著作権はサイトの権利者に帰属します。掲載に不都合がある場合、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。
- 当サイトからリンクよって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。