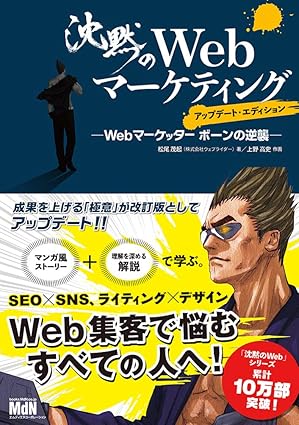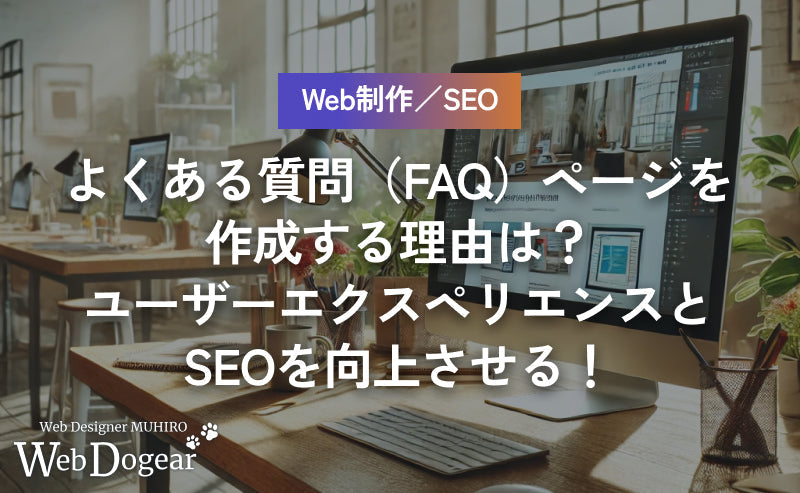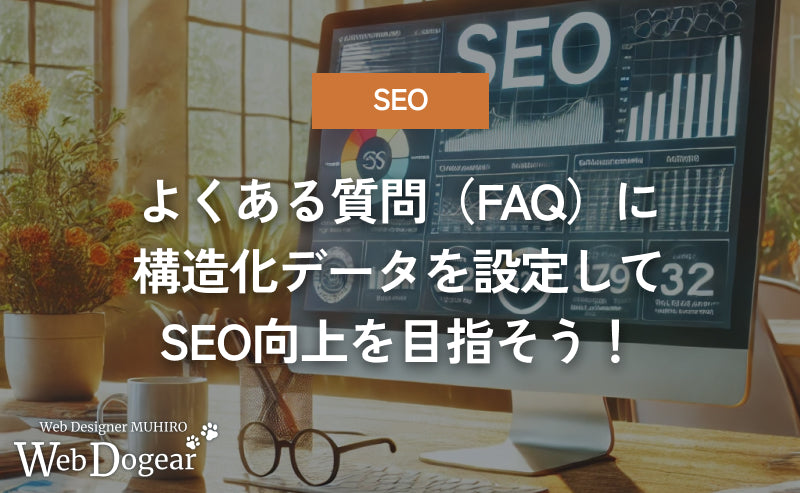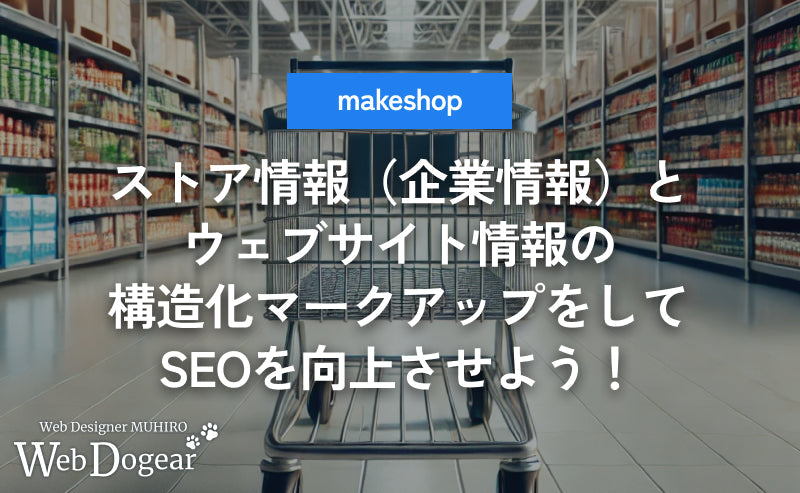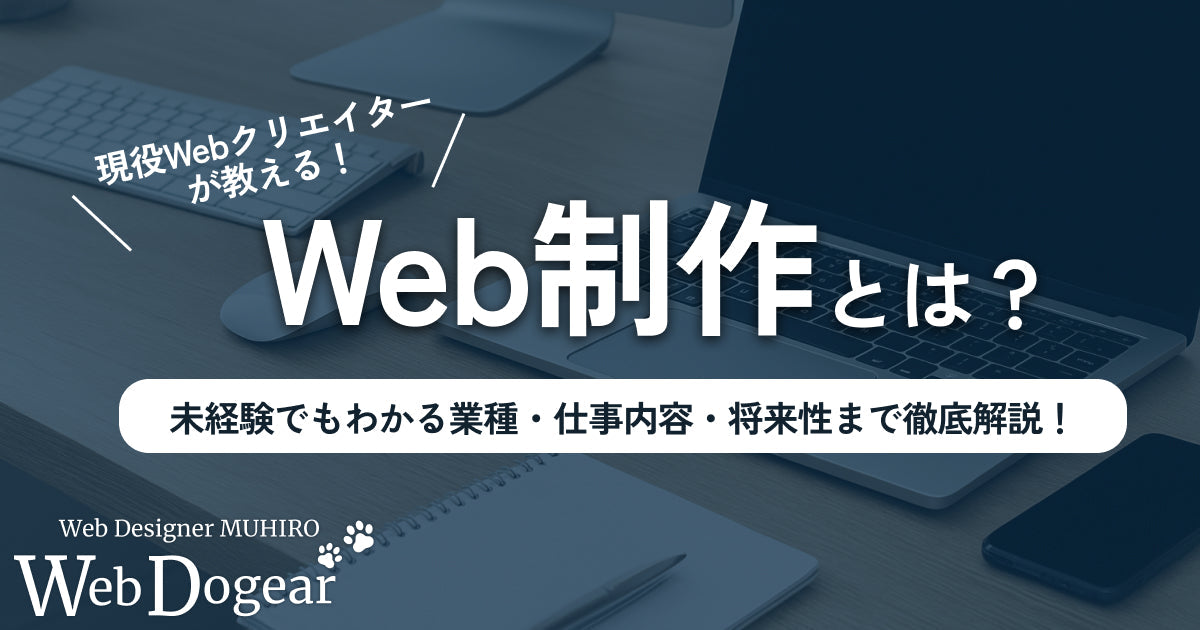構造化データと構造化マークアップの違いとは?SEOへの効果と導入のポイントを解説
Published: Updated:
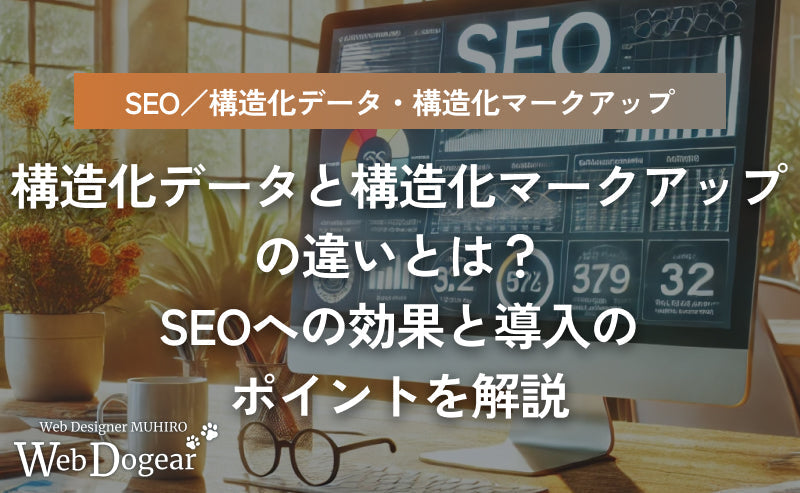
こんにちは、Webデザイナーの 夢拓(Muhiro)です。
「構造化データ」と「構造化マークアップ」、Webに関わる方なら一度は耳にしたことがある用語かと思います。
SEO対策を進めていく中で、Googleの検索結果に表示される「リッチリザルト(レビューやFAQなど)」に興味を持ち、実現するために調べていると、この2つの言葉に出会うことが多くあります。
しかし、それぞれの言葉の意味や役割の違いについては、意外と曖昧なままの人も多いのではないでしょうか。「なんとなく似てるけど、結局どっちを使えばいいの?」という疑問を持つ方も少なくありません。
この記事では、WebサイトのSEOに関心のあるWeb担当者やWebデザイナー、コンテンツ制作者向けに、「構造化データと構造化マークアップの明確な違い」、「SEOとの関係性と、どんな効果が期待できるのか」、「実際にどう導入すればいいのか」といった内容をわかりやすく解説します。
この記事を読んで、構造化データ・構造化マークアップの実践的なテクニックを使用して最適・高度な・柔軟なWebサイトを制作いただけるようになります!
それでは、どうぞ!
【初心者の方向け!】SEOを勉強したい方におすすめの書籍
Index
[ CloseOpen ]
構造化データ・構造化マークアップとは何か?
まず、用語の違いについて理解するために、それぞれの基本的な意味から押さえておきましょう。
構造化データとは?
構造化データとは、検索エンジンにコンテンツの意味を明示的に伝えるためのデータ構造です。
Web上で使われる構造化データは、主に「JSON-LD」「microdata」「RDFa」などの形式で記述され、Schema.orgという共通ルールに基づいて構造を定義します。
たとえば、レシピの記事に「料理名・調理時間・材料・作り方」などの情報が含まれている場合、それらを構造化データとして明示的にマークアップすることで、Googleがその内容を正しく認識し、リッチリザルトとして表示できるようになります。
構造化マークアップとは?
構造化マークアップとは、検索エンジンに内容を正確に伝えるために、HTMLに直接記述する特定のデータ構造です。
特に microdata や RDFa といった記述形式は、HTMLタグの属性として構造化データを直接埋め込む方法です。
HTML
手作りクッキー
PT30M
このようにHTMLタグに itemscope や itemprop などの属性を追加し、ページ内の情報に「意味」を与えていく作業こそが構造化マークアップです。
なお、JSON-LDはHTMLの構造とは独立して<script>タグ内に記述する形式であり、HTMLタグに直接属性を追加するmicrodataやRDFaとは実装方法が大きく異なります。そのため、厳密には「構造化マークアップ」よりも「構造化データの埋め込み」という表現の方が適切かもしれません。
構造化データと構造化マークアップの違いを比較
以下の表に、両者の違いをまとめます。
| 項目 | 構造化データ | 構造化マークアップ |
|---|---|---|
| 意味 | 意味情報をもったデータそのもの | データをHTMLに埋め込む記述方法 |
| 主な形式 | JSON-LD、microdata、RDFa | microdata、RDFa(HTMLタグ内) |
| Google推奨 | JSON-LD形式 | 一部サポート(主にmicrodata) |
| 記述場所 | <script>タグなど | HTMLタグ内 |
つまり、構造化データ = 情報そのもの、
構造化マークアップ = その情報をどうHTMLに埋め込むかという記述方法のことなのです。
【初心者の方向け!】SEOを勉強したい方におすすめの書籍
構造化データを使うとどんなSEO効果があるの?
検索結果にリッチリザルトが表示されやすくなる
構造化データを正しく実装することで、Googleがコンテンツの情報を正しく認識し、検索結果に目立つ表示(リッチリザルト)をしてくれる可能性が高まります。
これにより、クリック率(CTR)の向上が期待できます。
Googleは公式ドキュメントで「構造化データは検索エンジンがページを理解するのに役立ち、リッチリザルト表示の前提条件である」と説明しています。
リッチリザルトの表示対象になる要素
Google検索では、構造化データを正しく実装しているページに対して、「リッチリザルト」と呼ばれる拡張表示が可能になります。
以下のような要素です。
- 商品の価格・在庫状況・レビュー
- レシピの調理時間やカロリー
- よくある質問(FAQ)の展開形式
- パンくずリストの明示表示
- イベントの日程や場所
サイトの信頼性・専門性が伝わりやすくなる
検索ユーザーにとって、リッチな検索結果を出しているページは信頼感や専門性があるように映ります
これはE-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)の観点からも、SEOにおいてプラスに働きます。
インデックスの精度が向上する可能性
構造化データはクローラーがページを効率よく理解・分類するのに役立つため、インデックス登録の正確さやスピードの向上にも寄与します。
また、Googleは「構造化データの導入自体がランキングの直接的な要因ではない」としていますが、リッチリザルトの表示→CTRの向上→評価の向上といった間接的な効果は非常に大きいとされています。
JSON-LDの基本的な実装例
構造化データの中で最も推奨される「JSON-LD」を使った例を紹介します。
JavaScript
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Article",
"headline": "構造化データと構造化マークアップの違いとは?SEOへの効果と導入のポイントを解説",
"description": "構造化データと構造化マークアップの違い、SEO効果、実装方法について詳しく解説します。",
"author": {
"@type": "Person",
"name": "夢拓(MUHIRO)"
},
"datePublished": "2025-04-10T00:00:00+09:00",
"dateModified": "2025-04-10T00:00:00+09:00",
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "Web Dogear"
}
}
</script>
このように、HTMLに直接内容を混在させず、<script>タグの中で独立して記述するのがJSON-LDの特徴です。
SEOにも優しく、CMS(WordPress、Shopifyなど)でも導入しやすいため、現在はこの形式が主流です。
構造化データのチェック方法とおすすめツール
実装した構造化データが正しく認識されているかを確認するには、以下のツールを使うのが便利です。
- 構造化データ マークアップ支援ツール(旧ツール)Googleが提供していた構造化データ生成支援ツール(現在は廃止)
- 構造化データ テストツール(旧ツール)構造化データの検証ツール(現在は廃止、Rich Results Testに統合)
- Schema.org ValidatorSchema.org公式の検証ツール
実装時の注意点とよくある誤解
「構造化データを入れれば必ずリッチリザルトになる」は誤解
構造化データは「表示対象として考慮される」だけであり、表示されるかどうかはGoogle側の判断です。
ページの品質や信頼性、他の競合ページとの相対評価も関係します。
不正確なマークアップはペナルティの対象になる可能性も
たとえば存在しないレビューや誤った価格情報を構造化データでマークアップすると、ガイドライン違反としてGoogleの手動対策(ペナルティ)対象になることもあります。
構造化データを使う際は、必ず正確かつ信頼できる情報を記述しましょう。
構造化データとマークアップは併用可能?
構造化データとセマンティックなHTML(マークアップ)は併用可能であり、むしろベストプラクティスです。
HTML構造を整え、見出しタグやパンくずリスト、<article>タグなどを適切に用いた上で、構造化データを追加すると、検索エンジンへの情報伝達がより強固になります。
セマンティックマークアップとは?HTMLで意味を持たせるタグ設計
構造化マークアップで混同しやすいのが「セマンティックマークアップ(Semantic Markup)」です。
これは、HTML5で導入された意味を持つタグ(セマンティックタグ)を用いて、文書の構造や意味を明示するための記述方法です。
代表的なセマンティックタグ
- <header>ページや記事のヘッダー
- <nav>ナビゲーション領域
- <article>独立した記事ブロック
- <section>ページ内のセクション
- <time>時間の明示
- <h1>〜<h6>見出し構造
これらを適切に使うことで、検索エンジンやスクリーンリーダーがページ構造を正しく理解しやすくなります。
【初心者の方向け!】SEOを勉強したい方におすすめの書籍
この記事に関連するよくあるご質問
-
Qセマンティック(semantic)とは?
-
A
「意味」や「意味論」、「語義」などを意味。
Webサイトの構造や要素に意味を持たせる方法です。
単に見た目を整えるだけでなく、コンテンツの本質的な意味や役割を明確にすることを指します。例えば、見出しや段落、ナビゲーションなどに適切なHTMLタグを使用することで、検索エンジンやスクリーンリーダーがウェブページの構造をより正確に理解できるようになります。
これにより、Webサイトのアクセシビリティが向上し、SEO対策にも効果的です。
セマンティックなアプローチは、単なる見た目の装飾ではなく、情報の意味と構造を重視するWeb制作の重要な考え方なのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回の記事では、「構造化データ」と「構造化マークアップ」の違いや役割、そしてSEOにおける効果と導入ポイントについて解説しました。
今回のポイントをまとめますと、次のとおりです。
今回の記事のまとめ
- 構造化データは検索エンジン向けの意味情報を含んだデータ
- 構造化マークアップは、そのデータをHTMLに埋め込むための記述方法(microdataなど)
- 現在はJSON-LD形式が主流で、SEOではリッチリザルト表示に大きく関与
- 不正確なマークアップはSEOに悪影響を与えることもあるため注意
- Googleの公式ツールを使って確認・最適化を行うのが重要
他にも SEO対策 に関する 技術 や実用テクニックを随時発信しています。 「役に立った」と思っていただけた方は、ぜひブックマークやSNSでのシェアをお願いいたします!
最後までお読みいただきありがとうございました!
関連記事 Related articles
-
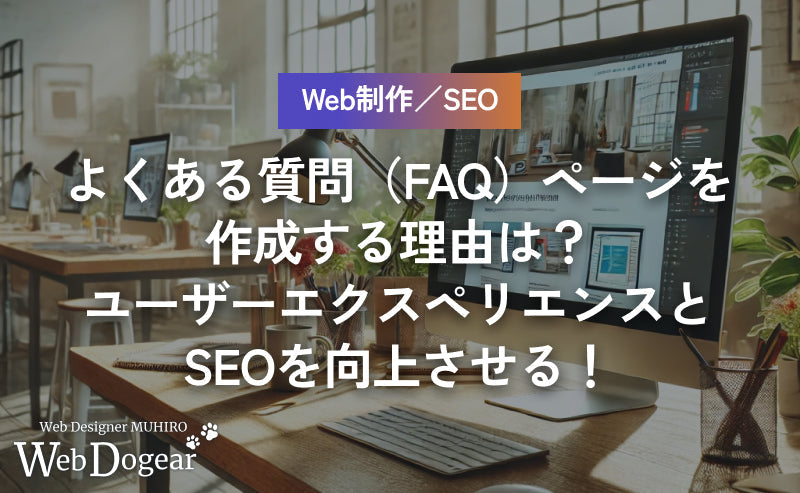
Published:
Updated:よくある質問(FAQ)ページを作成する理由は?デザインをしてユーザーエクスペリエンスとSEOを向上させる!
よくある質問(FAQ)ページを掲載しているホームページが多く見かけることはありませんか?制作会社の見積もりに含まれていて、「これって本当に必要なの?」と思ったことがある方もいらっしゃるでしょう。あるいは、SEO会社から作成を勧められた経験がある方もいるかもしれません。この記事では、そんな疑問を解決できるよう、よくあるご質問ページを作成すべき理由とSEO向上について解説をします。
-
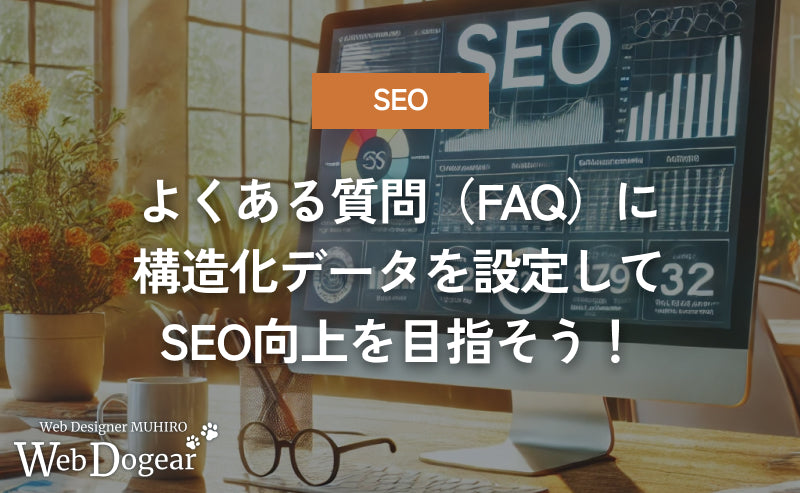
Published:
Updated:よくある質問(FAQ)に構造化データを設定してSEO向上を目指そう!
よくある質問(FAQ)ページに構造化データを導入したいけど、プログラミングがわからなくて断念してしまったことはありませんか?このような悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。私もそうでした。技術的なハードルが高いと感じていました。この記事では、初心者でも簡単によくあるご質問ページに構造化データを導入できる方法をご紹介します。
-
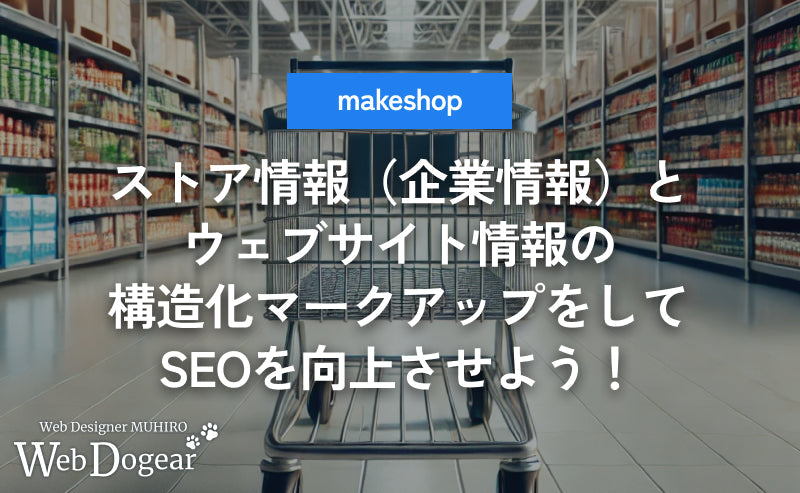
Published:
Updated:【MakeShop】ストア情報(企業情報)とウェブサイト情報の構造化マークアップをしてSEOを向上させよう!
ウェブサイトのSEOを改善するために、構造化マークアップの活用が重要になっています。 この記事ではMakeShopで作成したストアにストア情報(企業情報)とウェブサイト情報を構造化マークアップの方法を解説します。
-

Published:
Updated:【MakeShop】パンくずに構造化マークアップを導入してナビゲーションとSEOを強化しよう!
免責事項
- 当ブログでは、執筆者の経験に基づいた技術情報や知識を提供していますが、その正確性や普遍性を保証するものではありません。情報は執筆時点のものであり、技術の進展により古くなる可能性があります。これらの情報を利用する際は、自己責任で行ってください。必要に応じて専門家の助言を求めることをお勧めします。
- 当ブログで提供するプログラムコードは、執筆者の最善の知識に基づいていますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。コードの利用や実行により生じた損害や問題については、一切の責任を負いかねます。コードの使用は、自己責任で行ってください。
- 当サイトで使用しているスクリーンショット画像について、著作権はサイトの権利者に帰属します。掲載に不都合がある場合、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。
- 当サイトからリンクよって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。