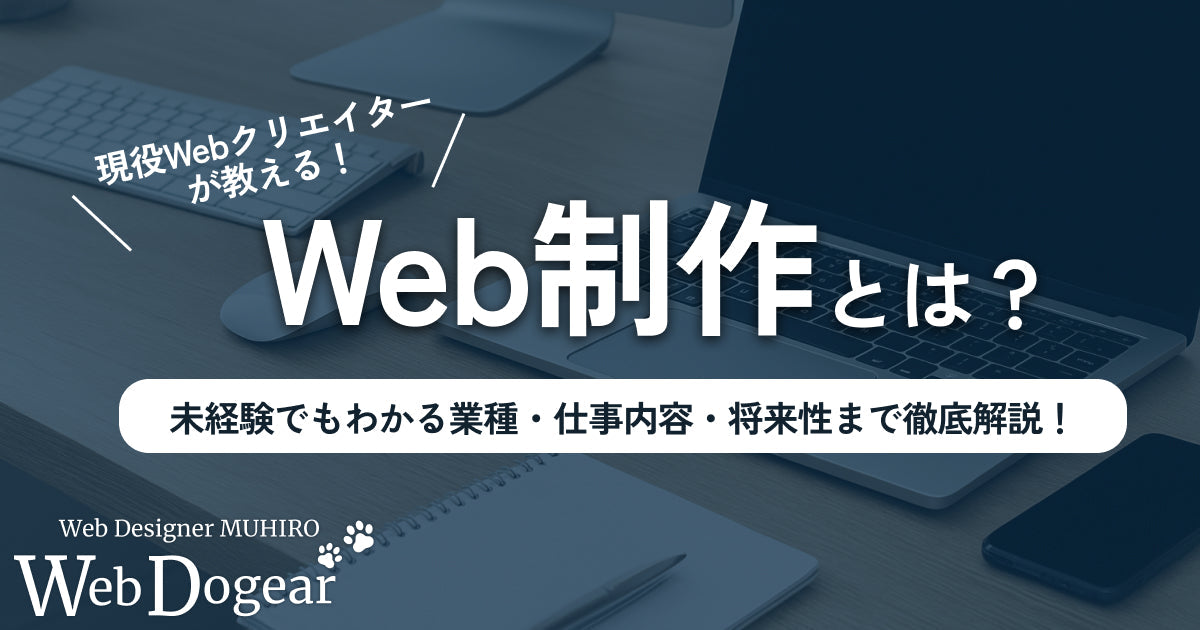【2025年最新版】GEO(生成エンジン最適化|Generative Engine Optimization)とは何か?AI時代のWeb集客を成功させる方法
Published: Updated:
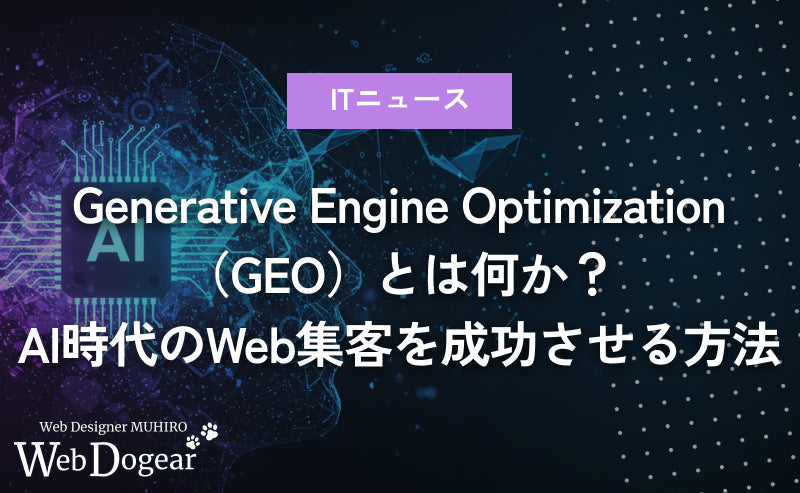
こんにちは、Webデザイナーの 夢拓(Muhiro)です。
近年、検索の在り方は大きく変化しています。
ChatGPT や Google Gemini、Claude などの生成AIが回答を提示する「AI検索」が急速に広まり、従来のSEO(Search Engine Optimization)だけでは十分な集客が難しくなっています。
そこで注目されているのがGenerative Engine Optimization(GEO)です。
本記事では、このGEOの最新動向から実践方法まで、最新情報をもとにわかりやすく解説します。
AI検索時代では、検索結果ページ(SERP)で上位表示されるだけでは不十分です。
生成AIが引用したくなる信頼性の高いコンテンツ設計や構造化データの活用が求められます。
GEOはまさにその課題を解決するアプローチであり、ブランドの認知やトラフィック獲得の新たな手段となります。
この記事を読んで、Generative Engine Optimization(GEO)の実践的なテクニックを活用し、AI時代に最適かつ高度で柔軟なWebサイト運営を行えるようになります!
Index
[ CloseOpen ]
Generative Engine Optimization(GEO)とは?
Generative Engine Optimization(GEO)とは、生成AI型の検索エンジンにおいて自社コンテンツが引用されやすくなるよう最適化する手法を指します。
従来のSEO(Search Engine Optimization)は検索結果ページ(SERP)での順位を上げることを目的としていましたが、GEOは生成AIが返す回答文の中に、自社の情報や文章を組み込ませることを重視します。
例えば、Googleの「AI Overviews」(2024年5月に米国で正式開始)やBing Chat、ChatGPTのウェブ検索機能などは、直接ウェブサイトを表示するのではなく、AIが複数の情報源をまとめた回答を提示します。
このとき、GEO対策を行っているサイトは、引用元として取り上げられる確率が高まり、間接的にブランド認知や流入が増加します。
研究では、GEO最適化により引用率が最大40%向上した事例も報告されています(出典:GEO‑bench, arXiv 2023)。
GEOが注目される背景と重要性
GEOが注目されている最大の理由は、ユーザー行動の変化です。
従来の検索エンジンはリンクをクリックして情報を得る形式でしたが、生成AI検索はその場で回答が完結するため、クリック数(CTR)が減少しています。
これにより、従来のSEOで上位表示してもアクセスが増えないケースが増加しました。
さらに、AI検索は情報の信頼性や構造化の度合いを重視する傾向があり、信頼できる引用元として認識されるためには、GEOの観点でのコンテンツ設計が不可欠です。
特にニュースメディアやBtoB企業では、AI経由でのブランド露出が購買や問い合わせに直結する可能性が高く、今後のWeb戦略の中心になると予測されています(出典:Search Engine Land「Generative Engine Optimization framework introduced in new research」2024年2月など )。

GEOと従来のSEOとの違い
GEOとSEOは目的や評価基準が異なります。
SEOはGoogleやBingなどの検索結果ページにおけるランキングを向上させることを目的としますが、GEOは生成AIの回答内に引用されることが目的です。
評価基準も、SEOはリンク構造やキーワード密度、ユーザー行動指標などが重視されますが、GEOは情報の信頼性、文脈の明確さ、構造化データ、そして引用されやすい文章構造が鍵となります。
また、SEOではタイトルタグやメタディスクリプションが重要でしたが、GEOでは見出し構造や段落ごとの情報粒度がより重要です。
これにより、同じコンテンツでもGEOを意識して再構築する必要が出てきています。
GEOの主要戦略・技術要素
- 構造化データの活用schema.orgなどのマークアップを使い、AIが情報を正確に理解できるようにします。
- 明確で簡潔な文章回答形式やFAQ形式を導入し、AIが抜粋しやすい形にします。
- 権威性と信頼性の証明出典リンクや統計データを活用し、情報の裏付けを行います。
- 更新頻度の最適化最新情報を反映し、AIに新鮮な情報源として認識されるようにします。
具体的な最適化手法とその実装例
具体的な手法としては、まず記事構成を見直し、段落ごとにテーマを明確化します。
さらに、重要情報を箇条書きや定義リストで提示し、AIが抽出しやすい形にします。
以下は、FAQ形式のHTML実装例です。
HTML
<div class="p-faq1">
<dl>
<dt>GEOとは何ですか?</dt>
<dd>Generative Engine Optimizationの略で、AI生成検索に最適化する手法です。</dd>
</dl>
</div>
AI生成回答で引用されやすいコンテンツ設計のポイント
引用されやすいコンテンツを作るためには、文章の明確さ・情報の信頼性・AIによる抽出のしやすさの3つを意識する必要があります。
以下では、それぞれの要素についてSEOも考慮した観点から詳しく解説します。
AIに理解されやすい文章の明確さ
明確さとは、情報を短く簡潔に提示し、読み手やAIが即座に理解できるようにすることです。
生成AIは長文からも情報を抽出できますが、冗長な説明は文脈の誤解や要約精度の低下を招きます。
そのため、1文あたりの情報量を絞り、重要なキーワードや数値は文頭に配置することが推奨されます。
また、見出しタグや箇条書きを活用して論点を明確化すると、検索エンジンとAIの双方が情報を抽出しやすくなります。
検索エンジンとAIに信頼される情報の信頼性
信頼性は、生成AIや検索エンジンが引用するかどうかを判断する最も重要な要素の一つです。
情報源としての権威性を高めるために、公式機関や一次情報を引用し、出典を明記しましょう。
出典には明確なURLと日付を含め、<blockquote>や引用用のHTML構造を使うことで、AIが参照関係を正確に把握できます。
また、信頼できる外部リンクを設定することは、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点からもSEO評価の向上につながります。
AIが情報を抽出しやすいHTML構造設計
抽出の容易さとは、生成AIが情報を切り出して利用しやすいコンテンツ構造を持っていることを意味します。
HTMLタグの正しい階層構造(<h2>〜<h4>の適切な使用)、箇条書き(<ul>)、定義リスト(<dl>)などによる情報整理は必須です。
FAQ形式を導入すれば、質問と回答のペアが明確化され、AIが誤った文脈で引用するリスクを減らせます。
さらに、画像や図解にはalt属性を最適化して内容を説明することで、ビジュアル情報もAIに認識させられます。
成果の測定とツール紹介(例:HubSpotのGrader、WixのAI Visibility Overview)
GEOの成果は、従来のSEOのようにアクセス解析だけでは測れません。
AI検索における引用率や、回答内での表示回数、ブランド言及数などを追跡する必要があります。
HubSpotの「AI Search Grader」はGEOの最適化状況を評価でき、Wixの「AI Visibility Overview」はAI検索での可視性を測定できます。
これらのツールを活用することで、GEO施策の効果を定量的に把握できます。
導入時の課題とその乗り越え方
Generative Engine Optimization(GEO)の導入には、技術面・運用面の両方でいくつかの壁があります。
以下では、GEO導入時によくある課題と、その課題を解決するための効果的な乗り越え方について詳しく解説します。
GEO導入時によくある課題
GEO(Generative Engine Optimization)の導入は、多くの企業にとって新しい分野であり、いくつかの共通した課題に直面します。
以下では、代表的な課題を詳しく説明します。
構造化データの実装難易度
GEOにおいては、schema.orgなどの構造化データを正確にマークアップすることが必須です。
しかし、この作業にはHTMLやSEOの技術的知識が求められ、不正確な記述は検索エンジンや生成AIの理解を妨げる恐れがあります。
特に大規模サイトや多言語サイトでは、テンプレートの設計段階から構造化データの仕様を組み込む必要があります。
コンテンツ再構築の工数
既存のコンテンツをAIに引用されやすい形に再構成するには、見出し構造の整理、段落の短文化、FAQ形式や定義リストの導入などが必要です。
ページ数が多い場合、編集に多くの時間と人的リソースが必要となり、通常のSEO改善以上の工数がかかります。
また、社内の承認フローやCMSの仕様によって、改修スピードが制限されることもあります。
AIアルゴリズムの変化
生成AIや検索エンジンのアルゴリズムは頻繁に更新され、以前有効だった施策が短期間で効果を失う可能性があります。
例えば、AIが引用する情報の優先順位や構造化データの評価方法が変わることがあり、継続的なモニタリングと改善が不可欠です。
成果測定の難しさ
従来のSEOではオーガニックトラフィックや順位が主要指標でしたが、GEOでは「引用率」「回答内でのブランド言及数」など新しい指標が重要です。
しかし、これらのデータは通常のアクセス解析ツールでは取得できない場合が多く、専用ツールやカスタムレポートの構築が必要となります。
GEO導入課題を解決する効果的な方法
上記の課題を解決するためには、戦略的かつ計画的なアプローチが求められます。
以下では、効果的な解決方法を詳細に解説します。
重要ページから優先的に最適化
全ページを一度に最適化するのではなく、まずはAI検索での引用価値が高いページから着手します。
例えば、企業のサービス概要ページ、よく閲覧されるブログ記事、業界特化のホワイトペーパーなどです。
これにより、少ないリソースでも早期に成果を確認できます。
構造化データのテンプレート化
一度正しい構造化データを設計・実装し、CMSやサイトテンプレートに組み込むことで、更新時の手間を大幅に削減できます。
特にイベント情報、製品データ、FAQなどの繰り返し構造にはテンプレート化が有効です。
定期的なGEO監査
半年から1年ごとにGEO監査を行い、AI検索での引用状況やブランド言及数を分析します。
監査結果に基づき、古くなった情報の更新、見出しや段落構造の最適化、構造化データの修正を行います。
成果測定ツールの導入
Wixの「AI Visibility Overview」やHubSpotの「AI Search Grader」など、GEOに対応した可視化ツールを導入します。
これらのツールを活用することで、従来のアクセス解析では見えなかったAI検索でのパフォーマンスを把握できます。
AIアルゴリズムの最新情報を収集
検索エンジンの公式ブログ、海外SEOメディア、AI技術の専門フォーラムなどを定期的にチェックし、最新動向を把握します。
情報更新のスピードに対応できる体制を作ることで、施策の陳腐化を防げます。
この記事に関連するよくあるご質問
-
QGEOとAEOの違いは何ですか?
-
AAEOはAnswer Engine Optimizationで、主にFAQや短文回答を最適化する手法です。
GEOはそれに加え、生成AIの回答文全体に引用されやすくする構造設計を含みます。
-
QGEO対策は全ての業種に必要ですか?
-
A全ての業種で必須ではありませんが、情報発信やブランド認知が重要な業種では有効です。
特にBtoB、メディア運営、EC事業では効果が高い傾向があります。
-
QGEOの効果はどれくらいで現れますか?
-
Aコンテンツや業種、AI検索エンジンの反映タイミングによりますが、早ければ数週間〜数ヶ月で引用増加が確認できる場合があります。
-
QGEO対策にはどんなツールが使えますか?
-
AWixの「AI Visibility Overview」、HubSpotの「Website Grader」、または専用の構造化データ検証ツールなどが活用できます。
-
QGEOとSEOは同時に行うべきですか?
-
Aはい、SEOとGEOは相互補完関係にあります。
検索エンジンでの順位向上とAI検索での引用増加を同時に狙うことで、より高い集客効果を得られます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回の記事では、Generative Engine Optimization(GEO)の概要、重要性、実践方法を解説しました。
今回のポイントをまとめますと、次のとおりです。
他にもGEOに関する最新情報や実践テクニックを随時発信しています。
「役に立った」と思っていただけた方は、ぜひブックマークやSNSでのシェアをお願いいたします!
最後までお読みいただきありがとうございました!
免責事項
- 当ブログでは、執筆者の経験に基づいた技術情報や知識を提供していますが、その正確性や普遍性を保証するものではありません。情報は執筆時点のものであり、技術の進展により古くなる可能性があります。これらの情報を利用する際は、自己責任で行ってください。必要に応じて専門家の助言を求めることをお勧めします。
- 当ブログで提供するプログラムコードは、執筆者の最善の知識に基づいていますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。コードの利用や実行により生じた損害や問題については、一切の責任を負いかねます。コードの使用は、自己責任で行ってください。
- 当サイトで使用しているスクリーンショット画像について、著作権はサイトの権利者に帰属します。掲載に不都合がある場合、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。
- 当サイトからリンクよって他のサイトに移動された場合、移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。